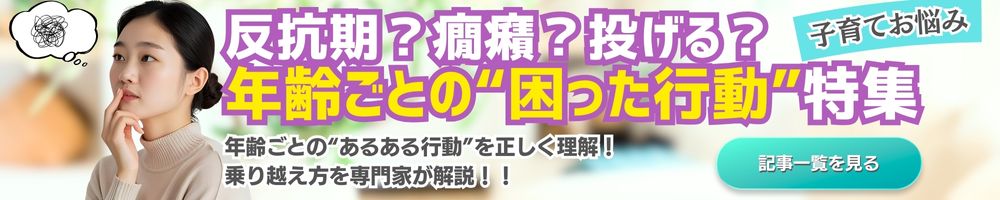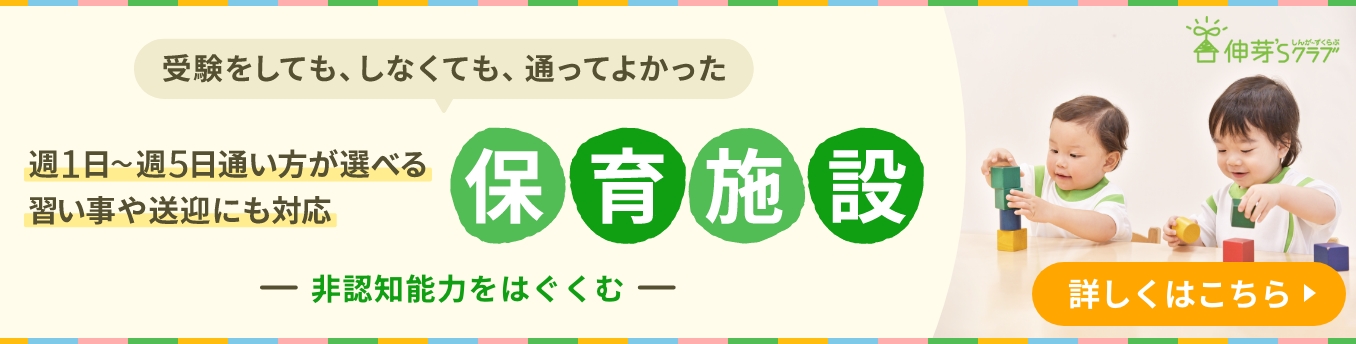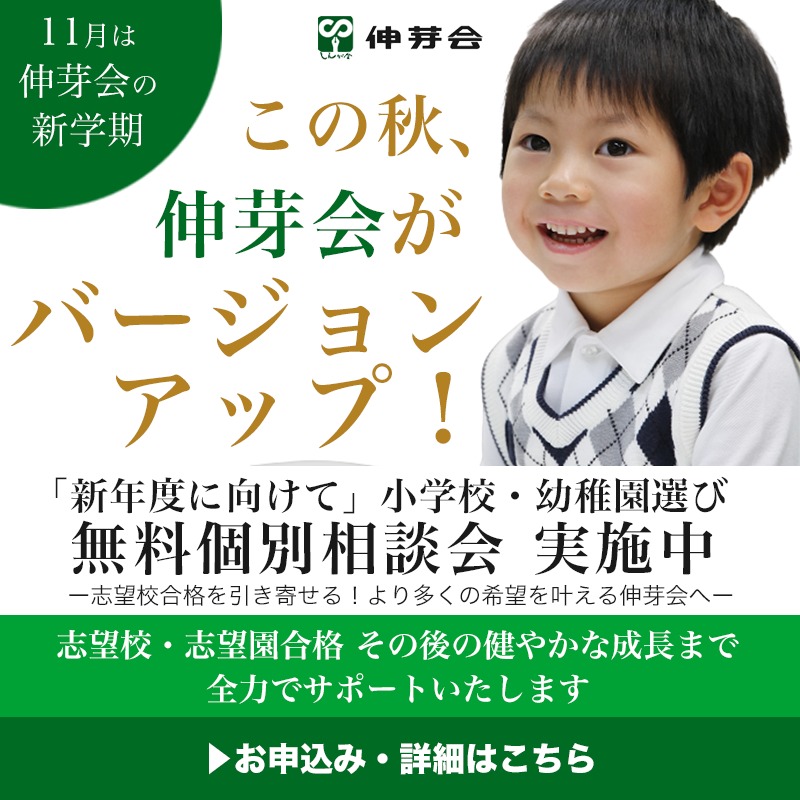7歳反抗期とは?原因と親の対応法を解説

小学校生活にもようやく慣れ、ホッとしたのもつかの間、今度は、「言葉使いが悪くなった」「親に反抗的な態度を取る」と新たな問題に頭を悩ませる親御さんは多いようです。悪態をつくさまは、立派な反抗期のよう!? 小学校低学年で見られる反抗、反発に親はどう向き合っていくべきなのでしょうか?
☑ 親が見直すべき2つの関わり方とは?距離としつけの再確認が鍵
☑ ハーシ博士のボンド理論に学ぶ、子どもとの絆の築き方
7歳反抗期とは?
7歳前後になると、子どもに突然現れる“言うことを聞かない”“やたら突っかかってくる”などの変化に、戸惑う保護者も多いのではないでしょうか。
この時期に見られる反抗は、「7歳の壁」や「7歳の危機」と呼ばれ、子どもの内面の成長と深く関わっています。
子ども自身も「なんだかうまくいかない」と感じやすい年齢で、親や周囲の大人に反発的な態度をとったり、妙に理屈っぽくなったりすることがあります。
たとえば、指示に対して「でも」「だって」と言い返したり、気に入らないことがあると急に不機嫌になったり――そんな行動が目立つようになるのです。
ただし、これは単なる「わがまま」や「悪い態度」ではありません。7歳頃の反抗は、子どもが自分の考えや感情を持ち始めた証。自分なりの世界観をつくろうとしている“心の成長の過程”なのです。
一次反抗期・二次反抗期との違い
子どもの成長過程には、いくつかの「反抗期」と呼ばれる時期があります。
中でも、「一次反抗期(2〜3歳ごろ)」「7歳反抗期」「二次反抗期(思春期)」は、それぞれ現れるタイミングや理由、反抗のあらわれ方に違いがあります。
一次反抗期(2〜3歳ごろ)
いわゆる「イヤイヤ期」です。自分でやってみたいという気持ちが芽生え始める一方で、うまく言葉にできず、かんしゃくや大声、否定的な言葉で親に反発することが多くなります。
自己主張の始まりとも言えるこの時期は、感情のままにぶつかってくるのが特徴です。
二次反抗期(思春期)
思春期に入ると、「親とは違う自分でいたい」「干渉されたくない」といった自立心の高まりから、口数が少なくなったり、親の言うことに強く反発したりするようになります。
対話を拒んだり、感情をぶつけたりと、関係が難しくなることもある時期です。
「7歳反抗期」は心の葛藤が反抗として表れている
7歳ごろに見られる反抗は、内面の発達にともなう“こころのゆらぎ”が大きく関係しています。親や先生に対して「なんで?」「でもさ…」と疑問や反論を口にしたり、急に不機嫌になったりすることがありますが、その背景にはこうした心の成長があるのです。
「相手の期待に応えたいけど、自分の気持ちも大事にしたい」
「正しさを求めたいけど、自信がない」
「本当は甘えたいけど、かっこよくいたい」
このような心の葛藤(ジレンマ)が、「反抗」という形で現れてくるのが、7歳反抗期の特徴です。大人の目には理屈っぽく映るかもしれませんが、本人にとっては真剣そのものなのです。
他にも、7歳反抗期の特徴や理由についてはこちらの記事に詳しくまとめています。ぜひご参考ください。

ピアジェ博士の発達理論から見た7歳反抗期の理由とは?
7歳反抗期を防ぐ2つの確認事項
「うちの子、なんでこんなに歯向かってくるんだろう」と感じたら、ぜひ次の2つのことを再確認してみてください。
【7歳反抗期を防ぐ確認その1】距離の再確認
子どもは徐々に自立をしていくものですし、親もその自立を上手に促していきたいものです。しかし、幼稚園卒園から小学校入学まで、わずか1ヵ月しか経たないのに、急に子ども任せにしてしまっても上手くはいきません。
とくに1年生のうちは、それまでとは違った集団生活にとまどうため、家庭を心のよりどころにしたい思いが強まります。ですので、小学校に入ったから距離を開けるのではなく、むしろ入学したからこそ、環境の変化へのとまどいを受け止めるためにも、距離を縮めるくらいの方が望ましいと言えます。
もし、「最近は一緒に遊ぶことも少なくなった」「ゆっくりおしゃべりする機会も減った」と感じたら、その部分から距離を縮めていきましょう。しっかり引き寄せてあげると、安心して子どもの方から離れていけるようになります。
【7歳反抗期を防ぐ確認その2】しつけの再確認
小学校に上がると、外で過ごす時間が増えます。親から離れている時間が増える分、外にいるときにも抑制がきくようなしつけをしているかがカギになります。
「○○しなさい」「○○はダメだよ」と言ってくれるママがそばにいなくても、ある程度の社会的なマナーは満たせないと、お友達との関係が上手く保てなかったり、先生に怒られることが増えたりしてしまいます。
この時期のしつけのポイントで大事なのは、他者へのリスペクトです。かりにあいさつがきちんとできなくても他人に迷惑はかかりませんが、騒いではいけない場面で騒ぐのは、周りに迷惑をかけます。ママがそばにいるときのしつけだけでなく、離れたときにきちんと作用するよう、他者に対してどうか、社会でどうかをポイントにしつけの見直しをしてみましょう。
ハーシ博士のボンド理論で社会的絆を意識しよう
お子さんとの距離、離れている時間のためのしつけ、この2つについてお伝えしてきましたが、前者は子どもとの絆や愛情を再認識するための甘党アプローチ、後者はお子さんの外での集団行動で求められるマナーやルールを意識した辛党アプローチと言えます。
アメリカの社会学者ハーシ博士は、自身の提唱したボンド理論で、“社会的絆”が非行や逸脱の抑止要因となっていると言っています。属する社会とのしっかりとした絆があることが、子どもの抑制力につながるということです。
甘辛のバランスが崩れた状態―つまり親との距離が開き、外での抑制がきかない状況―で社会との絆が希薄になってしまうと、親や先生への反抗心を生み出したり、問題行動をして怒られても反省せずに逆切れしたりというような状況に陥りかねません。
7歳という年頃は、実際にはまだまだ親を安全基地として、甘え行動を欲しています。小学校という本格的な社会生活がスタートし、周囲からも「しっかりしっかり」と自立を求められるため、中には素直に甘えられない子、感情を吐露できない子もいます。
それを踏まえ、これまで以上に、親には“察する力”が求められていることを意識することが、この時期の反抗を緩和するポイントと言えるでしょう。

子どもの中間反抗期とは?特徴とパターン別対処法を解説!

相談の場「育児相談室ポジカフェ」&学びの場「ポジ育ラボ」を運営。
専門は0~10歳のお子さんを持つご家庭向けの行動改善プログラム、認知行動療法ベースの育児ストレス支援。ポジ育ラボでは子育てに関する心理学情報を発信するほか、ママ・パパが自分の心のケアを学べるメルマガ講座「ポジ育クラブ」を配信。英・レスター大学大学院修士課程修了。HP:https://megumi-sato.com/