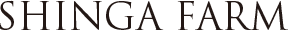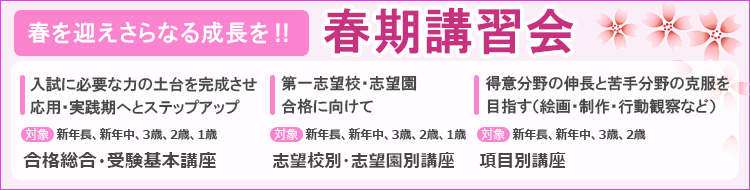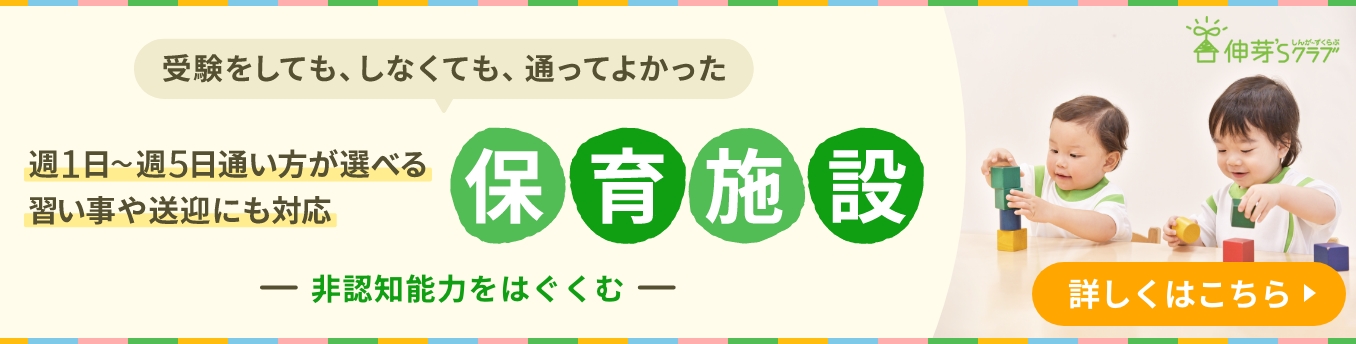ママが抱える育休明けの不安、どう対策する?【公認心理師解説】

育休が明け、職場に復帰するタイミングは、子どもの保育園生活のスタートでもあるため、親子ともに日常が様変わりします。子どもが馴染めるか、生活が回るか、仕事との両立ができるかなどの思いが頭をめぐり、不安にならない人はおそらくいないのではないでしょうか。育休明けの不安対策について、公認心理師の佐藤めぐみさんが解説していきます。
目次
育休明けの仕事復帰で生じる3つの不安とは?

私の相談室は、数ヵ月、数年と長きに渡り利用されている方も多いので、その過程で職場復帰を迎える方も多くいらっしゃいます。
お話をお聞きすると、だれもが「復帰への不安」を抱えており、しかも内容がかなり共通していることに気づかされます。先輩ママたちのリアルな声はきっと多くの方の参考になると思いますので、ここでご紹介していきます。
その1 子どもへの不安
「子どもに寂しい思いをさせてしまうのではないか」
「慣らし保育で順調に馴染めるか」
「楽しく過ごしてくれるだろうか」
「復帰はこの子にとって正しい決断なのか」
その2 仕事への不安
「仕事のペースが取り戻せるか」
「職場に迷惑をかけないか」
「時短勤務への理解をしてもらえるか」
「自分のキャリアが保てるか」
その3 両立への不安
「子どもの生活リズムが崩れないか」
「突発的な病気などの呼び出しに対応できるか」
「仕事が忙しい日のお迎えのやりくりができるか」
「夫婦間の連携がどこまでうまくいくか」
「体力的に回るのか」
自分の現状と比べて、重なるところもあったのではないでしょうか。
頭の中に不安をさまよわせていると、エンドレスに膨らみがちです。上記のように、具体的な自分の不安点をリストにしてみると、それだけでもだいぶ楽になることがあります。向き合うべきことが可視化されるからです。ぜひ自分が何に不安を感じているかを具体的に書き出してみましょう。
不安別の対処法

不安というのは“不確定な未来”に対して起こるものです。それらの不確定要素に対し、自分の中である程度の“確定”を約束できると、不安は静まりやすくなります。上記で挙げたような不安リストに対し、自分なりの着地点を決めておくということですね。
以下に、どんなことをポイントにしたらいいのかをまとめていきます。
●子どものこと
園への適応についての不安
慣らし保育が始まる前から、公園や児童館などで子ども同士で触れ合う機会を積極的に設けて、家以外の場への慣らしを始めておきます。とくに人見知りが強い子は慣れるまで時間が必要なことが多いので、復帰前の一緒にいられる時間から「外に慣れる練習」をスタートさせていくのがおすすめです。
急な体調不良についての不安
病児保育の事前手続きを済ませ、その流れを確認しておく。在宅勤務への切り替えはできるかの相談をしておく。祖父母など周りに助っ人を頼めそうか検討する……。
このように、当日の受け皿の見通しを立てておきましょう。
●仕事面のこと
復帰自体への不安
長い期間ブランクがあると、元のように働けるかと心配がつきまといますが、知識のアップデートは不安軽減に有効です。復帰後に現場で学ぶことも多いと思いますが、できる予習はしておけると安心です。
働き方への不安
時短勤務をする場合、当然ながら会社と事前に話し合って取り決めているものですが、急な呼び出しなどの突発事項についても触れておきたいものです。ここは職場によってかなり温度差があるところだと思うので、夫婦で出した対応策を聞いてもらいつつ職場の温度を把握し、それを踏まえてできうる対応の目星をつけておきましょう。
●自分自身のこと
両立への体力面での不安
頼れるものは頼り、省けるものは省く、がやはりカギですが、仕事と育児と家事で言うなら、家事が一番の対象です。仕事は効率化できても、お金をいただいている以上省略はできませんし、育児は省くと後々どこかにひずみが出てくるものです。
その点、家事は家電や外注など自分以外に頼ることができます。食洗機などの家電、食材の宅配、ファミサポやベビーシッターなどの人的サポートなど。優先順位を明確にし、手放せることは手放していきましょう。
・家事・育児の代行サービスに関してはこちらの記事をご覧ください。

幼稚園ママでも働ける!「ママのできる」をシェアで仕事に
両立への精神面での不安
体力面の部分とも関係してきますが、1日の流れを“理想的にし過ぎないこと”がまずはとても重要です。ここは「自分は完璧主義傾向がある」と自覚している人ほど要注意です。
これまでの育児の日々で「思ったようには進まない」のは感じていると思うので、“すべてがうまくいかないと回らないスケジュール”はうまくいきません。計画段階で多少の余分な時間がない場合は、どこかで見直しをかけておくことを強くおすすめします。
私たちの不安は、先々の「もしも」を考えると発生するので、「もしも○○になったら、~~すればいい」と答えまで導いておくことがポイントです。
答えのない「もしも」ばかりを頭の中に乱立させないためにも、①自分が不安に思っているのは何か、②それに対してできそうなことは何か、を書き出してみましょう。
新生活が楽しくなる工夫をしよう

ここまでずっと不安対策について述べてきましたが、新生活が楽しくなる工夫を考えておくこともとても大事です。私がこれまでにお話ししてきたママたちも、
・ネイルをきれいにキープする
・お迎えに行く前に時間を作ってたまにお茶をする
・子どもが寝た後に夫婦でお酒やお菓子をたしなむ
・会社の同僚と週1は外にランチに行く
・夫婦で協力し、週末に1人時間を作り合う
・少し先のお出かけの予定を立て、早めにお得に予約する
など、自分なりの“お楽しみ”を工夫していました。
ひと言でまとめるなら、
「大人の時間を持つ」
でしょうか。こういう時間を組み込むと、しんどい毎日でも多少バランスが取りやすくなるのだと思います。
ただ現実は、こういう時間こそ、優先順位が最下位にされがちで、「結局自分の時間が持てなかった」というのも非常によく聞く話です。こういうお楽しみの時間は、あらかじめ設定しておかない限り永遠にやってこないことが多いので、夫婦で協力し合って、それぞれのお楽しみタイムを確保していきましょう。
・夫婦のスケジュール管理についてはこちらの記事をご覧ください。
復帰後に振り返る時間を持とう

ここまで復帰前に感じやすい不安に対する対策をお伝えしてきましたが、実際に復職すると、思っていたようにいかないことも多々あるもの。私の相談事例を振り返っても、ビフォーの段階での想定通りにはいかず、微調整をかける方が多い印象です。
その多くが、「時間が思い通りに進まない」という問題です。復帰前に立てる計画は理想を求めがちなので、復職して実際の感覚がわかったら、あらためて振り返る時間を設け、持続可能な形に組み直しましょう。
タイミングとしては、復帰してから1ヵ月過ぎたあたりでしょうか。というのも、復帰当初は気も張っているし、「ちゃんとやらないと」と踏ん張っているので、まだまだ“日常”とは言い難いからです。
そんな時期を超え、いよいよ日常になってくると、「疲れが出てきた」「うまく回らない」「イライラが止まらない」のような不具合を実感することが多いので、そこでいったん仕切り直しをかけると地に足のついた計画が立てやすいと思います。
基本的にその段階でやることは“引き算”です。「もっと省く」「もっと頼る」という方向性でメンテナンスをしていきます。
最後に大事なことを。育児ストレス全般に言えることですが、同じことをやるにしても、自分がその状況を統制できているかどうかで心の在り方は大きく変わってきます。
「自分が回されている感覚」だと置かれている状況に支配されてしまっているためとてもしんどくなります。「自分が回している感覚」だと、たとえ忙しくても気持ちいい汗を感じることができます。
今ある状況の中で、「自分が回されている感覚」から「自分が回している感覚」へ持っていくには何ができるか、という視点も復帰後の生活のバランスを整える上で大事なのです。

育児相談室「ポジカフェ」主宰&ポジ育ラボ代表
イギリス・レスター大学大学院修士号(MSc)取得。オランダ心理学会(NIP)認定心理士。ポジ育ラボでのママ向け講座、育児相談室でのカウンセリング、メディアや企業への執筆活動などを通じ、子育て心理学でママをサポート。2020年11月に、ママが自分の心のケアを学べる場「ポジ育クラブ」をスタート。著書に「子育て心理学のプロが教える輝くママの習慣」など。HP:https://megumi-sato.com/