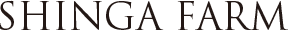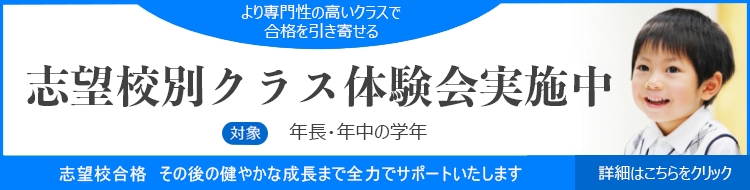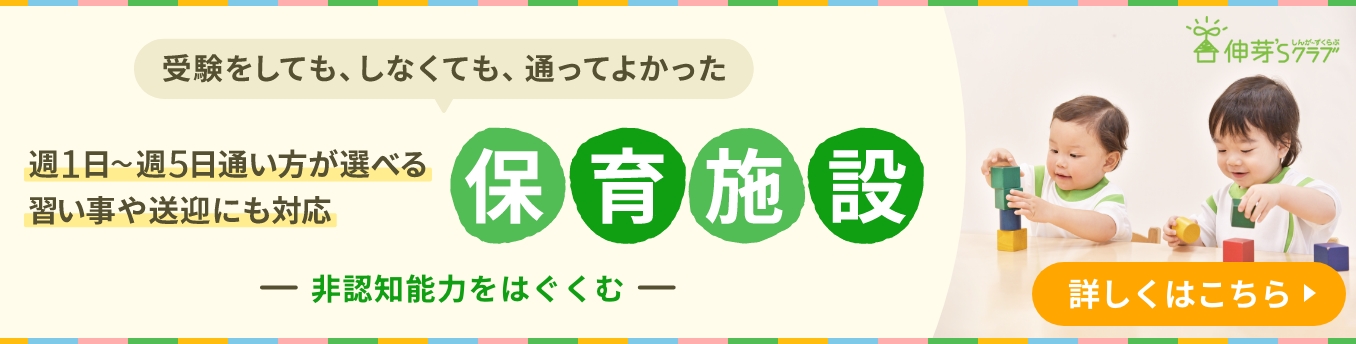近視は病気!?子どもの視力低下は遺伝でなく環境で決まる【眼科医監修】

2024年7月、文部科学省から「小中学生の50.3%が近視に」という衝撃的な発表がありました。日本は他のアジア諸国と比べて、近視抑制の積極的な取り組みがなされていないと言われております。
そこで、『近視は病気です』(東洋経済新報社)の著者で、近視抑制眼鏡『クボタグラス』の開発者である窪田良先生にお話を伺いました。近視の予防法や最新の治療法も必見です!
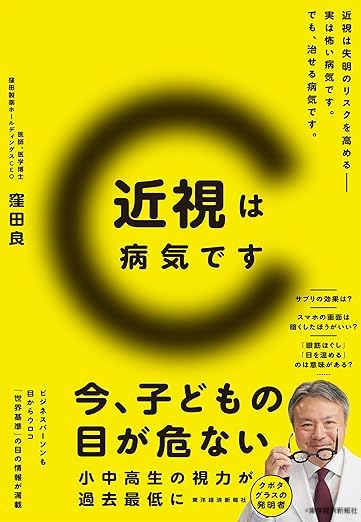
窪田良先生
医師・医学博士・窪田製薬ホールディングスCEO。慶應義塾大学医学部卒業後、同大学の客員教授、米NASA HPP研究所代表者などを歴任し、アメリカに2002年創薬ベンチャー・アキュセラを創業。2016年に窪田製薬ホールディングスを設立し、本社を日本に移転。現在は糖尿病網膜症の研究や、NASAと共同で在宅医療モニタリングデバイスや近視デバイスの研究を行う。近著『近視は病気です』(東洋経済新報社)が発売中。
HP:https://www.kubotaglass.jp
目次
子どもたちの視力低下が止まらない!

__世界的に見ても、近視の子どもたちは増えているのでしょうか?
文部科学省の2023年の調査によると、裸眼視力1.0以下の子どもの割合が、小学生で約38%、中学生で約61%、高校生で約72%といずれも過去最多を更新しています。日本だけではありません。過熱する受験の影響もあり、アジアでは20歳以下の約8割が近視という結果も出ています。
また、WHOは、「2050年には世界人口の約半分が近視になる」と予測し、2024年9月に「近視を病気とすべき」と国立アカデミーが提言してます。これは、地球温暖化やマイクロプラスチックによる海洋汚染などと同様に、「近視を地球規模で減らしなさい!」という忠告なのです。台湾やシンガポール、中国ではすでに対策をして近視が減り始めていますが、日本では関心が低く野放し状態です。
その警告の意味も込めて、今回『近視は病気です』(東洋経済新報社)という本を書かせていただきました。
近視は遺伝でなく環境で決まる!

__子どもの視力について、「親が知っておきたいこと」を教えてください。
赤ちゃんは生まれたときは強い遠視で視力は0.1程度、1~2歳で0.5程度、10歳で1.0程度になっていきます。多くの場合6~12歳で近視が出始め、14~18歳で進行が止まるため、視力は「20歳までの眼球成長期の過ごし方が最も重要」になってきます。
そして声を大にしてお伝えしたいのは、「視力は遺伝よりも環境で決まる!」ということです。両親が近視でも、子どもの目の環境を変えれば、近視を発症しない可能性が十分ありますし、「眼鏡をかけても環境に配慮しなければ近視は悪化する」ことがあります。
ぜひ「わが子の近視は対処しようがない」と諦めるのではなく、早めに発見しつつ予防してほしいのです。
加えて、日本は近視対策が海外と比べて遅れをとっているのが現状です。たとえば近隣の台湾では、身長体重と同じように、親がわが子の目の状態を視力と度数まで把握していますし、中国では1年に2度子どもの視力を検査しています。日本では年に1度の視力検査はあると思いますが、できれば度数と遠視・乱視の程度も調べておくとよいでしょう。
__わが子の視力低下のサインはありますか?
子どもは自分では目が悪くなったことに気づきにくく、片目だけがよく見えていることもあるので、定期的に検査をすることが大切です。
視力低下のサインとしては、「目を細めて物を見る」「物を近くに寄せないと見えない」「見るときに顔を傾ける」「よく目をこする」「瞬きが多い」などがあります。他にも、「充血している」「焦点が定まらない」「まぶしがる」「痛みを訴える」場合は、遠視や弱視、斜視など近視以外の病気の可能性もあります。
また、小学生以降「本を読むスピードが速くならない(読みたがらない)」「勉強が進まない」「ボールをうまくキャッチできない」といった場合も、目がよく見えないため避けていることもありますので、一度小児専門の眼科の受診をおすすめします。
幼少期の運動量が視力低下を防げる?視力悪化を防ぐ対策4つ

__子どもの視力悪化を予防するために、できることはありますか?
・1日2時間の外遊びをする
太陽光の明るさと波長が目によい効果をもたらすことは証明されています。そのため、近視を発症しやすい6~12歳は1日2時間の屋外活動(日陰でもOK)で近視を予防できます。散歩でも買い物でも構いませんから、窓で遮断された光ではなく、外で太陽光を浴びる時間を確保しましょう。極論ですが、スマホやゲームは屋内よりも木陰やベランダでするほうが目への悪影響は少ないのです。
・スマホやタブレットはできるだけ見ない
近視の子が増えた要因のひとつに、スマホやタブレットなど近いところで見る時間(近見作業)の増加が挙げられています。中国では近視を減らす政策が2021年から導入され、子どものゲーム時間が制限されたニュースが話題になりましたが、日本では家庭の判断に任せているため、個人的には「見せすぎ」だと感じています。
・テレビの前に物を置かない
近くを見すぎると、ピント調節機能が固まって仮性近視や老眼と同じ状態になることがあります。昔から、「テレビを近くで見ない」と言われているのは正解なのです。さらに、テレビから離れて見ていても、手前のテーブルなどにものがあると、網膜がそこにピントを合わせようとしてしまうため、手前に物を置かないようにしましょう。ちなみに、テレビの画面の大きさは視力にあまり関係がありません。
・サングラスやブルーライトカットはむしろ有害!?
視力低下を防ぐには、いろいろな波長の光が入ることが重要だと言われています。そのため、ブルーライトだけをカットすることはむしろ有害だという研究もあります。
サングラスに関しても同様で、視力の観点ではビタミンDの合成にはUVも必要です。海外や晴れた雪の日など特殊な環境をのぞきますが、日常生活において日本人の目の色であれば、紫外線はさほど健康に影響しないという研究も出ています。あまり神経質になって、幼児にサングラスやブルーライトカット眼鏡をかけさせる必要はないと私は考えています。
近視は治る?わが子にあった治療法の選び方

__子どもの近視の治療法にはどんなものがありますか?
近視の研究は世界的に見てもアジアが最先端です。各国で差はありますが、現在日本で行われている近視の代表的な治療法は以下の通りです。
その①近視抑制の目薬「アトロピン」
2024年の12月に厚生労働省で「アトロピン」という近視抑制の目薬が認可されました(自由診療)。副作用や長期の点眼の懸念点もゼロではありませんので、専門医にご相談ください(費用は診察代別で点眼1本あたり4,000円程度)。
その②手術しない近視矯正法「オルソケラトロジー」
寝ているときに専用のコンタクトを装着して、角膜の形を変えて視力を改善させる治療法です。エビデンスも出ており、何より日中は裸眼で過ごせるので、最近ではポピュラーな近視の治療法になっています。とはいえ、好みや合う合わないがあります(費用は初年度15万~20万円程度)。
その③クボタグラス
私どもが開発した近視抑制をもたらす特殊な眼鏡です。遠くを見ているような映像環境や自然光独特の波長、明るさなど視力によい3つの要素を入れたもので、1日1~2時間かけて生活するだけで外遊びと同じ効果が得られます。まぶしさや痛み、つらさがないため、体の負担が少なく、6歳から使用可能です(価格は70万円)。効果は以下で解説しています。
__近視の治療は何歳から始めればよいですか?
基本的には近視を発見し次第、度数-0.5程度が治療開始の目安ですが、両親が強い近視であれば、小学校入学前からの治療も有効です。近視の度数にもよりますが、中国では近視の発症前から予防する傾向もあります。お子さんは生まれた瞬間から近視に向かっていますから、普段の生活でいかに近視を予防するかがポイントとなります。
また、子どもの眼鏡のフィッティングや度数計測はとても難しく、眼科医の中にも得意でない人も多いため、できれば小児眼科に行くことをおすすめします。
外遊びと同じ効果が得られる眼鏡「クボタグラス」とは?

__なぜクボタグラスを開発しようと思われたのでしょうか?
「近視を世界から撲滅するデバイスを作ること」を目的として開発しました。眼鏡にした理由は、子どもにとって点眼やコンタクトよりも負担が少ないと考えたからです。
たとえば、虫歯は予防の認識が広まり、幼児の虫歯は減少傾向にあります(令和4年厚生労働省「歯科疾患実態調査結果」より )。虫歯と同じように近視も抑制・治療できるのです。将来、近視がなくなって「眼鏡ってあったんだ!」となるのが理想です。
__クボタグラスの効果を教えてください
2022年に発売し、米国では最も高い安全基準が必要な小児用メディカルデバイス認証(ISO13485)を取得しています。効果としては、オルソケラトロジーやアトロピン点眼などが近視低下のスピードが半分(50%)になるのに対し、クボタグラスは現段階のデータだと抑制率が101%とわずかに視力がよくなっています。
クボタグラスを1時間かけるだけで効果が表れた人もいます。現在、台湾で長期試験を行っていますが、将来的にはアトロピンやオルソケラトロジーとの組み合わせでさらに効果を高めることも検討しています。
一人ひとりの度数や顔の大きさに合わせて作るため、現在の価格は70万円と高価なのが目下の課題です(一生涯のコンタクト代を考えると高くはないという声もありますが)。ニーズが高まり、大量生産できるようになれば価格を下げられると考えています。
取り扱い眼科医・眼鏡店などはHPをご覧ください。

【眼科医インタビュー】コロナ禍で加速する子どもの視力低下。原因や対策は?
SHINGA FARM(シンガファーム)編集部が執筆、株式会社 伸芽会による完全監修記事です。 SHINGA FARMを運営する伸芽会は、創立半世紀を超える幼児教育のパイオニア。詰め込みやマニュアルが通用しない幼児教育の世界で、毎年名門小学校へ多数の合格者を送り出しています。このSHINGA FARMでは育児や教育にお悩みのご家庭を応援するべく、子育てから受験まで様々なお役立ち情報を発信しています。
X(旧Twitter)、Instagram、Youtubeちゃんねる、Facebookにて最新更新情報やオリジナルの動画コンテンツを発信中!ぜひフォローください♪