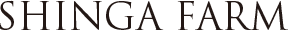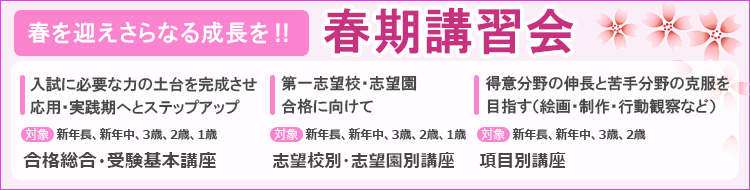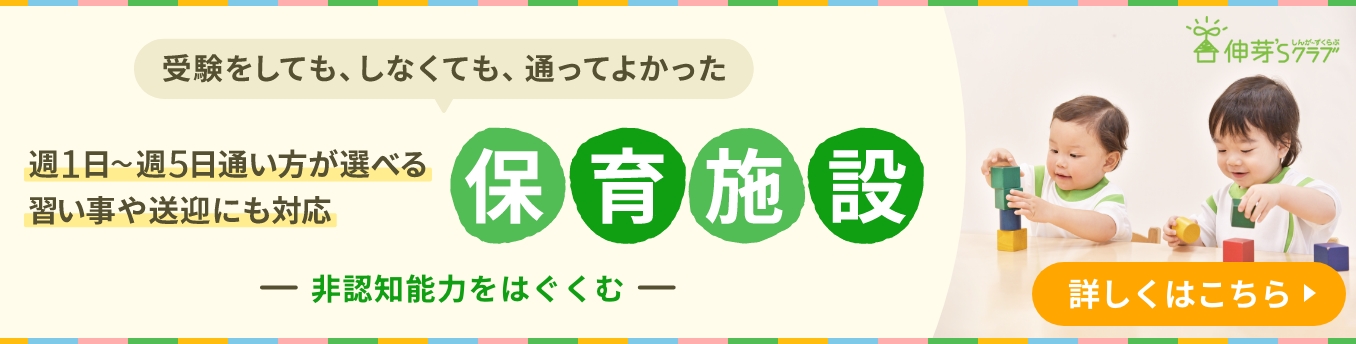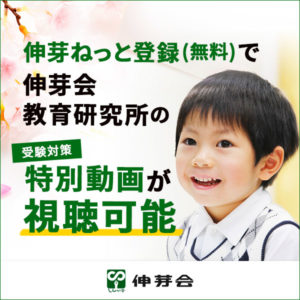家庭でできる、子どもの「考える力」を伸ばす取り組み

前職の右脳教育の幼児教室では、0歳〜小学校4年生までの各クラスの担任を担当し、100組程度のご家庭と関わる機会をいただきました。
講師時代に多くの育児相談をお受けしたことから始めたカウンセリングサービスでしたが、改めて子育てに対する不安は尽きることがないんだと日々実感しています。
現在私がカウンセリングを行う中で多く受ける相談をもとに執筆していますが、同じ悩みを持つ保護者の方の不安の種を取り除く一助となれば幸いです。
第二回目のテーマは「家庭でできる、子どもの考える力を伸ばす取り組み」です。ぜひご家庭で実践していただけると嬉しいです。
目次
記憶から思考の時代へ
私たちは、これまで記憶がメインの教育を受けてきました。教科書を丸暗記していればテストでは大体良い点数が取れていましたよね。「勉強」の9割以上が記憶だったと言っても過言ではありません。
しかし、今それが変わろうとしているんです。
今年2020年には学習指導要領の改訂が行われ、教育改革が実施されますね。その背景にはAI化の加速などが挙げられます。
記憶は、AIの方が断然得意ですから。じゃあ人間はどういう力を身につけるべきなの?と考えたときに、私は思考が大きなキーワードになってくると考えています。(参考:https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201903/2.html)
思考というと、ロジカル思考とか、クリティカル思考とか、近年色々なキーワードが出てきていますが、まずはシンプルに、自分で考え、判断すること、という定義でお話していきたいと思います。
考えることが苦手な子どもの特徴
考えることが苦手な子どもは、「あなたはどう思う?」と聞くと、「わからない」と答えます。本来なら自分の考えを聞かれているのに、「わからない」という回答はおかしいですよね?
これは、質問には必ず、「答えがある」ことが当たり前だと思っているから出る回答であり、従来の記憶型の教育の価値観が染み付いてしまっているということです。この「わからない」は、「答えを探したけどわからない」と同義なのだと思います。
では、そのような状況はなぜ生まれるのでしょうか?それは、保護者の皆さんが受けてきた教育を、そのまま実践しているからだと思います。
ドリルの問題を解きこなすことは、いわば記憶でしょう。「考え方」を覚えてその通りに実践するだけなので、マニュアル通りの対応です。
実際に、これを実感した出来事がありました。
私が幼児教室で働いていた時、小学校2年生の男児2人のクラスの担当をしていました。小学生になってから教室に通い始めた有名私立小の生徒と、0歳から通っていた公立小の生徒でした。私はこの二人を見て、「思考」の種類が違うと思いました。
有名小の生徒は初見の問題になるとすぐに諦めて違うことをやり始めていましたが、もう一人の生徒は「あーでもない、こーでもない」とブツブツ言いながらとても楽しそうに問題を解いていたんです。
お受験がいいとか、悪いとか、そのような話ではなく、解き方を教えられ、それを忠実に再現してきた子どもからすると、新しい問題をどのように解くか考える、といった思考回路がそもそもなかったんですね。
子どもが楽しく考えながら学べる機会を、大人には作る責任があると思いました。
ハクシノレシピ レッスンでの実例
考えることが苦手な子どもの特徴について、先ほどは教育メインでのお話をしましたが、実はもう一つ大きな要因があります。それは「間違えることが怖い」という意識です。特に未就学児など、小さいお子さんに多く見られます。
ハクシノレシピでは、「どう思う?」など、子ども自身に考えてもらうような質問を多くします。やはり、「わからない」というお子さんはとても多いのですが、私たちはそのような場合に「先生はこう思うよ!」と言って意見を述べたり、わざと一般的ではないことを言ってみたりすることで、正解はないよ、思ったことを言っていいんだよ、ということを伝えるようにしています。
そうすることで、子ども達は安心をして自分の意見を言えるようになります。
実際に4歳の女の子のレッスンの時、お肉はジュージューしたら何色になると思う?と聞くと、緊張した面持ちで「わからない」と言っていましたが、「もしかして、緑かもー!?」と先生が言ってみると笑ってくれて「私は茶色くなると思う!」と伝えてくれました。
いざ焼いてみると茶色に変化したので、「すごい!Aちゃんが言ってた通り茶色になったね!先生は間違えちゃったけど、とても勉強になったよ!Aちゃんありがとう!」と伝えると、とても嬉しそうにしていました。
それ以降、質問に対して「わからない」と答えることが少しずつ減っていき、自分の考えを述べられるようになりました。
家庭でできること
間違えてもいいんだ!と子どもが感じられるような声かけは、ぜひご家庭でも取り組んでいただきたいです。例えば、一緒にお絵かきをしている時に、「ママの顔書いてー!」と、ピンクのクレヨンを渡したり。わざと間違えて「ママ失敗しちゃったー!」と言ってみたり。お母さんが間違えたり、失敗したりすると、子どもがそれらを恐れなくなります。
逆に「ああしてね、こうしてね」と先回りして手を差し伸べてしまっては、失敗してはいけない圧力に感じるようになってしまいます。保護者の方自身が正解に囚われず、楽しみながらお子さんと向き合うことが何よりも大切です。
ハクシノレシピより、LINEカウンセリング無料受付のお知らせ
今回コロナウイルスの感染拡大防止のため、小学校の休校、幼稚園、保育園の休園など、子どもと過ごす時間がいつもより増えています。そのような中で、保護者の方がそのようなモヤモヤを抱える機会が増える可能性が高いにも関わらず、それを発散できる場はなかなかないのが現状です。
ハクシノレシピでは、そのような保護者の方のモヤモヤの発散の場となり、子どもと過ごす時間をより楽しいものにできるよう、会員様以外にも無料でカウンセリングを提供することといたしました。
詳しくは下記リンクからご覧ください。
https://peraichi.com/landing_pages/view/hakurepi3