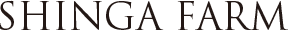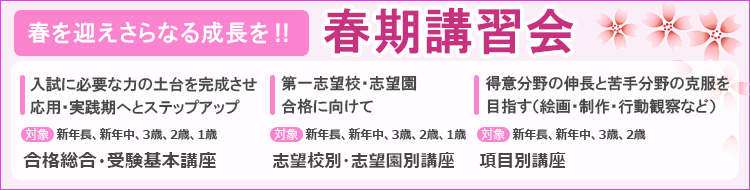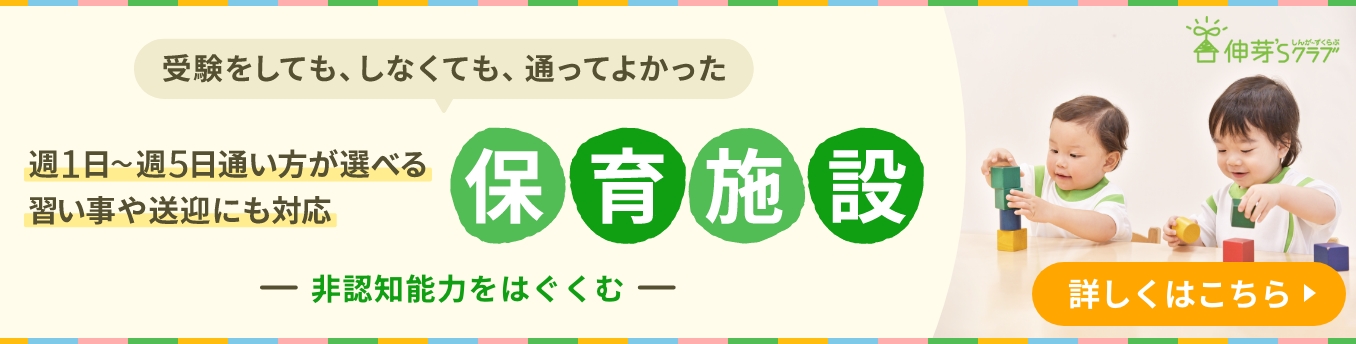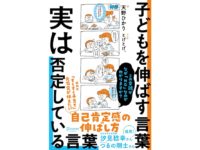人の話を聞かない子どもの原因と「聞く力」の高め方【伸芽会監修】

文部科学省では「これからの時代に求められる国語力」 として4つの力(聞く・話す・読む・書く)を掲げていますが、中でも最近は子どもたちの「聞く力」が低下していると言われています。また、わが子が「人の話を聞かない」と悩む親御さんも増えています。そこで今回は、子どもの聞く力を伸ばすコツを伸芽会の佐藤眞理先生にアドバイスいただきます。
目次
幼児期の聞く力の大切さ

まず、聞く力が足りないと、どんなときに困るかを考えてみましょう。
・大事なことを聞き逃してしまう
・集団生活で周りに迷惑をかけてしまう
・自分の領域を狭めてしまう
・人の言うことへの理解が不十分なため、コミュニケーションがうまく取れない
これを見ると、親御さんは「やっぱりうちの子には聞く力をつけないと」と思われるかもしれません。ですが、本来子どもは自分の好きなことだけをやっていたい生き物です。
私は、聞く力が足りないというのは、以下のようなよい面もあると考えています。
・夢中になれるエネルギーが高い
・すべての学習の基本となる「探究心」が強い
・自分の世界がある(周りに流されない)
つまり、大事なのは、「話を聞かない=ダメ」ではなく、親が子どものよき理解者になることなのです。
まず、話を聞かないのは「どうしてもやりたい事がある」「自分だけの世界に閉じこもっている」など、その子なりの理由がある事を認めてあげましょう。
その上で、「ちゃんとお話を聞いているとこんないいことがあるよ」「お話の通りにするともっと楽しいことがあるんだよ」と、お子さまの世界を少しずつ広げて、社会性や協調性、仲間との達成感を身につけていきましょう。
・聞く力の重要性に関しては、こちらの記事もご覧ください。
最近の子の「聞く力」が低下している理由

長年幼児教室で子どもたちを見てきましたが、最近の子は「聞く力」だけではなく「話す力」も低下していると感じます。
その主な理由として、
・家の中で親御さんに話を聞いてもらう時間が少なくなっている
・親が先回りして話を要約してしまう
・動画などを見て時間を過ごす“受け身な遊び”が増え、自ら発信する機会が少ない
今は子育てをしながらお仕事をされている方も多いので、物理的にわが子に関わる時間がとれず、やむを得ず動画を見せて遊ばせることもあるでしょう。
また、一見会話をしているようでも、親が答えを誘導するような質問(子どもは「うん」と言うだけ)や、親が話を要約してしまうため、子どもも自分の言葉で話していないのにしゃべった気分になってしまうことも多いのではないでしょうか。
つまり、聞く力が低下している原因の一つは話す力不足、つまり親子のコミュニケーションの取り方にも問題があるのです。
家庭の中で「聞く力」を伸ばすには?

では、具体的に家庭の中でできる「聞く力を伸ばすコツ」についてお伝えしていきます。
意識したいポイントは以下の通りです。
・してほしいことをきちんと言葉にして伝える
・家庭の中で会話の量(語彙)を増やす
・目を見て話を聞く習慣をつける
・意識的に人とのつながりを作る
・自尊心をくすぐるなど、子どもが聞きたくなるような言い方をする
「早くしなさい」「これをやりなさい」など指示ばかりして、「なんで?」と聞かれると
「いいから早く!」と答えてしまうことはありませんか?
それでは、子どもの反発心を刺激こそすれ中々やる気になりません。子どもとしっかり向き合い、言葉で理由を伝え、乳幼児期からたくさん話しかけて会話の量を増やしていきましょう。
その際、親が料理やスマホをしながら話を聞くのはNGです。短い時間でもよいので、目を見て相槌をうちながら話を聞くことで「自分の話を聞いてもらう喜び」を感じることができます。
年齢別の具体的な関わり方のアドバイスは以下の通りです。
0~2歳頃
まだ言葉がわからないお子さまにもたくさん話しかけてあげましょう。感情表現を豊かにするためにも、声色を変えて楽しさやさびしさを感じさせたり、絵本で悲しい顔をしている場面が出てきたら「どうして泣いているんだろうね」と聞くことで人の気持ちを考えるきっかけにもなります。
3~4歳頃
ごっこ遊びを好む時期ですが、その際、登場人物を増やしていくことで会話が広がります。「パパに食べさせてあげよう」でもいいですし、ぬいぐるみの「くまさんに持っていってあげよう」でもOKです。その後「パパはなんて言ってた?」などと聞けば、聞く意識を働かせられます。ポイントは会話を広げ、発展させることです。
5~6歳頃
年長くらいになったら、誰かに「聞いてもらう」機会を増やしましょう。おじいさんおばあさんにお手紙を書いたり、自分で絵本を作って家族に発表してみるなど、伝えることで得られる反応や、喜びを体験してほしいですね。
何より、親御さんは「ちゃんと聞きなさい!」と強要するのではなく、「聞いてもらえる工夫」をすることも大切です。何かに夢中になっているお子さまには「これもできるかな、できたらすごいんだけどなぁ」など、自尊心をくすぐるような伝え方も効果的です。
「聞く力」は小学校受験でも効果を発揮!

小学校受験では「聞く力」を問う問題も多数出題されます。なぜなら、小学校は集団授業をする際に話を聞けない子ばかりだと、授業にならないからです。
また、受験でも聞く力は全ての問題の基本です。実際、小学校入試後に幼児教室で「どんな問題だった?」と子どもたちに聞きとりをするのですが、問題をよく聞いて、それをきちんと伝えられる子に合格者が多いのも事実です。
聞く力は問題を把握する力そのものです。さらに話す力でその理解度を示すことができます。たとえば、「公園でいけないことをしている絵」を見せて、いけないこととその理由を問う問題があります。子どもたちは、絵を見て「花壇の花をとる」「滑り台を逆から上る」などダメなことはわかっても、理由を聞くと「危ないから……」しか言えない子がとても多いのです。
今の時代、学校が望むのは「自分で考えた答えが言える子」ですから、その先の「どう危ないか」「なぜしてはいけないのか」までを考えて自分の言葉で言える子が合格を勝ち取る子たちです。その際、大人が正解を教え込むのではなく、「お花が可哀そう」「ぶつかったらケガをして痛いから」など、お子さま自身の考えを引き出してあげるようにしましょう。
・小学校受験に合格する家庭の共通点はこちらの記事をご覧ください。

幼児教育のプロが語る! 小学校受験に合格する家庭と子の共通点!
【まとめ】
聞く力を伸ばすには家庭でのコミュニケーションが不可欠であり、小学生以降の集団生活が始まる前の幼児期にこそ伸ばしたい力と言えます。
そのためには、小さいうちから親子でたくさん会話をすることが大切です。そうすることで、聞く力や話す力、語彙力が増え、結果的に小学生以降の学力向上や社会性や人間性が育つことにつながるのです。
・親子のコミュニケーションと語彙力の関係については、こちらの記事をご覧ください。

子どもの語彙力格差はママとの会話で決まる!

2歳から小学生まで。「言うことを聞かない!」の年齢別特長と対処法

「〇〇もうやった?」でなぜ子どもはへそを曲げるの?
SHINGA FARM(シンガファーム)編集部が執筆、株式会社 伸芽会による完全監修記事です。 SHINGA FARMを運営する伸芽会は、創立半世紀を超える幼児教育のパイオニア。詰め込みやマニュアルが通用しない幼児教育の世界で、毎年名門小学校へ多数の合格者を送り出しています。このSHINGA FARMでは育児や教育にお悩みのご家庭を応援するべく、子育てから受験まで様々なお役立ち情報を発信しています。
X(旧Twitter)、Instagram、Youtubeちゃんねる、Facebookにて最新更新情報やオリジナルの動画コンテンツを発信中!ぜひフォローください♪