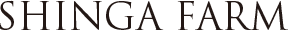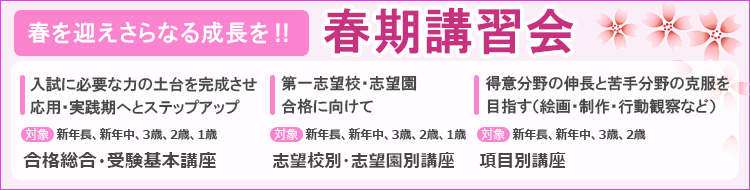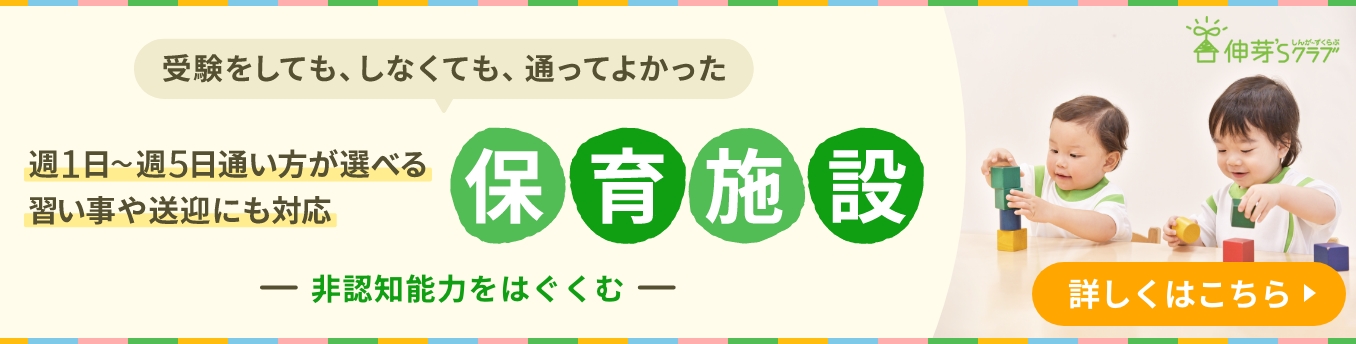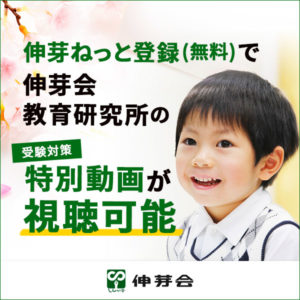【公認心理師監修】外遊びの効果とは? 五感を刺激しスクリーンタイムも短くなる!

外出が気持ちいい季節になりました。そこで今回はあらためて外遊びの魅力について見ていきたいと思います。公認心理師の視点から、外遊びで期待できる子どもの心へのメリットについてもお伝えしていきます。
目次
外遊びが1日30分以下!? 内遊びになりがちな現代
子どもの外遊びが減っているというのは、おそらくだれもが実感していることだと思います。外遊び推進の会のホームページに掲載されているデータによれば、1~6歳の子の平均的な外遊び時間は、1日30分以下なのだそうです。この数字を見てどう思われましたか? 「こんなに少ないんだ」と感じた方も多いのではないでしょうか。
下の表は子どもたちの遊び時間の内訳です。これを見ると、遊び時間の大半がテレビやビデオの視聴時間であることが見えてきます。この調査は2016年度のものなので、その後のコロナ禍で外遊びはさらに減少したと考えられます。
※セル内の数字は上が男児で下が女児です。
| 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 6歳児 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊び時間 | 162分 155分 |
164分 157分 |
156分 150分 |
149分 140分 |
143分 135分 |
136分 131分 |
| そのうちの外遊び時間 | 23分 21分 |
28分 25分 |
28分 25分 |
28分 25分 |
30分 25分 |
27分 25分 |
| テレビ・ビデオ視聴時間 | 73分 71分 |
90分 85分 |
96分 93分 |
102分 96分 |
104分 99分 |
107分 104分 |
*参照:外遊び推進の会:https://kodomo-sotoasobi.com/
2020年の非常事態宣言のときに、ニュースなどで「子どもの遊び場がない」「体力が発散できない」という訴えを多く聞きました。きっとそのニュースを見た人は、いつも元気いっぱいに外で駆け回っている子が、コロナ禍で家に居ざるを得ない光景を思い浮かべたことでしょう。しかしこの調査結果を見ると、もともと外で遊んでいる時間が少なかったことがわかります。実際にはそもそもかなり減っていた外遊びがコロナ禍でさらに深刻になったというのが現実に沿った見方だと思われます。
世界保健機関(WHO)はスクリーンの前で過ごす子どもたちが世界的に増えている状況を鑑み、小さい子を持つご家庭に1日あたりのスクリーンタイム(画面の前で過ごす時間)の目安を提示しています。それによれば、2歳未満は見せないのが望ましく、2歳以降は1時間までとのこと。このガイドラインの背後には、画面の前にいる時間が長くなると、それだけ座って動かない時間が増えるという考えがあります。
スクリーンタイムと同じページに、体を動かす推奨時間についても明記されており、1歳以降は1日3時間以上、とくに3歳からは活発な動きを1時間以上含めることを勧めています。外で3時間遊びなさいと言っているわけではありませんが、家にいると気づいたらテレビを見ているというのは上記の日本の調査でも明らかなので、家の中であっても体を動かすことを意識する必要がありそうです。
外遊びがもたらす体と心へのメリット
外で遊ぶことのメリットは数えきれないほどあります。すぐに思いつくのは体へのいい影響でしょう。
- 体力がつく
- 運動能力が伸びる
- 体が丈夫になる
- よく眠れる
- 健康維持につながる
- お腹がすいて食欲が増す
これらは代表的な外遊びのメリットと言えます。
そして体だけでなく、心へのメリットもたくさんあります。以下は、外遊びをおすすめする心理学的な理由です。
対人コミュニケーションの場を得られやすい家の中で遊ぶ場合、基本的には家族と遊ぶことになりますが、外に出ると、出会いの数が広がります。公園などでいつものお友だちと遊ぶということもあれば、その場に居合わせた子と遊ぶということもあるでしょう。いずれにしても家の中にいるよりは多くの出会いがありますので、その子の社会性発達への良い刺激になると考えられます。
自己防衛を学ぶ機会になる同じ転ぶのでも、家の中よりも外の方が事が大きくなりがちです。そういう理由で家の中で遊ばせることを選んでいるご家庭もあると思いますが、カーリングペアレントに代表されるような先回りは、親がデコボコ道を平たんに整えてしまうため、子ども自ら、「これは大丈夫だろうか」と問うチャンスを逸してしまっています。失敗したり、少々痛い思いをすることで学べることは多いので、公園などで見守りながら冒険させることは、自ら考え、守る力を養う機会になるでしょう。
自信と勇気がわく新しい場所や人が苦手という場合、もともとの性格も影響していることが多いものです。とは言え、消極的な子がもし「こわいから」と家の中でずっと過ごしていたら、社会に出るのをさらに怖がるようになってしまいます。「こわいな」という思いは慣れを起こすことで「大丈夫だ」と変わっていくことが知られています。毎日少しずつでも外の新しい刺激に触れていけると、段々と慣れが起こり、それが自信や勇気につながっていきますので、内気な子ほど外に出る機会を増やしてあげてほしいと思います。
ゼロからの発想力を養う機会になる子どもは外に出ると、ひょんなことを遊びにすることがあります。落ちている小石や枝を集めたり、縁石を平均台にしたり……。おもちゃではないものを遊び道具にするこのような経験は発想力や創造力などに結びついていくものです。家の中の遊びは、すでに遊び方が決まっているものが多いですが(パズル、ブロック、折り紙など)、外だとおもちゃが転がっているわけではないので、何もないところから遊びを生み出そうとするのです。
応用力や臨機応変さを磨ける外での遊びは行き当たりばったりになることも多いものです。家の中にあるおもちゃほど繊細さはありませんので、その分自由な発想でルールを決めたり、その場でアレンジしたりと、その場で楽しもうと色々と考えます。そういう経験の中での「プランAがうまく行かなかったからプランBをやってみよう」というような試行錯誤は、物事に対して臨機応変に対応している場面そのものです。置かれた場面にフレキシブルに対応できるようになると、ストレスも抱えにくく、前向きな視点で物事を見ることにもつながるでしょう。
このように、外遊びは体にも心にも良いことばかりで文句のつけようがありません。これを機に、ぜひ意識的に取り入れていってほしいと思います。
植物、飛行機、生き物……家にはないものから五感を刺激しよう!
外遊びの時間を有意義なものにするには、家の中ではできない経験をするのがおすすめです。外には家の中にはないものがたくさんありますので、それらで五感を刺激してあげるのが望ましいでしょう。
家の中になくて外にあるもので思いつくものとして、解放的な空間や自然環境が挙げられます。広がる空には飛行機、公園への側道にはたんぽぽ、足元を見ればアリや石ころ。どれも家の中にいたら、絵本かテレビの中でしか見られないものがリアルに存在します。
また、たまたますれ違ったおばあちゃんに声をかけてもらったり、散歩中のワンちゃんを触らせてもらったり。家の中と比べ、外の環境がいかに刺激が多いかわかりますよね。
ですので、まずは外に連れ出してあげるのがとても大事。家の中で遊ぶことに慣れているお子さんの中には、外に行くのを嫌がる子もけっこういますが、多くの場合、テレビなどへの執着が見られます。親の方はテレビの視聴時間の長さを懸念していることが多いので、これを機に見直しを図り、外に出る機会を定期的に作っていけると一挙両得だと思います。
外遊びは型にはめずに好奇心を伸ばそういざ外に出るとなると、「何したらいい?」と迷ってしまう方も多いようですが心配にはおよびません。外遊びで一番大切にしてほしいのは、お子さんの興味だからです。
ドイツで行なわれたある研究で、子ども時代の遊び方と大人になってからの社会的な成功や自己評価には相関が見られたそうです。それによると、子どものときに「自由な遊び方をしていた」と答えた人たちの方が、社会への適応性が高く、目標に向けて臨機応変に進め、自尊心が高い傾向があったとのこと。ここでの自由な遊び=外遊びとは限りませんが、どこで遊ぶにしても親が決め過ぎないことはポイントになると思います。
親はつい子どもを楽しませたいという思いから、「あの公園に連れて行ってみよう」と遊びの枠がある場所を選定してしまうものです。でももしかしたら、その子は公園に行く手前のアリの行列の方に興味を持つかもしれません。
そういうとき、親が自分なりの外遊びの定義を用いて、公園へ引っ張って行ってしまうよりは、アリの行列をその日の外遊びにしてしまう方が、その子の興味に沿った自由な遊び方になります。大人が考える「こうあるべき」にはめこまないことは、外遊びのメリットを享受する上でもとても大事なポイントと言えます。
公園好きなフランス人に学ぶ! 外遊びを習慣にする3つのコツ
外遊びは体力増強にもつながりますので、たまのイベントにせずに習慣にしていきたいもの。この部分は私が以前長く住んでいたフランスでの人々の行動スタイルが参考になりそうですのでご紹介したいと思います。
フランス人はとにかく公園好きです。公園というよりも芝生好き、ピクニック好きと言えるかもしれません。パリなどの都心部は家が狭いこともあると思いますが、気温と時間が許す限り、外に出るのです。我が家も自然とそうなっていったのですが、そのときのことを振り返ると、習慣にするにはいくつかコツがあるように思います。
●その1 日々の導線に組み込む小さい子がいる家庭では、園や学校が終わってから、そのまま公園に流れることがほとんどで、共働きのご家庭はシッターさんが子どもたちを連れていきます。レジャーシートや砂場道具などほぼ毎日使うものを詰め込んだ“外遊びバッグ”を持ってお迎えに行き、その足で外遊びへと向かうのです。家に帰らずそのままというのが定着化のコツだったように思います。
●その2 敷居を低くする週末になるとお昼を持って公園に行くこともよくあり、春から秋にかけては芝生はどこも大賑わいです。お弁当を持参してピクニックとなると、「早起きして準備しなきゃ」と大ごとに思えてしまうのですが、フランスではその部分がとてもラフです。よく見かけたのは、バゲットを道中で購入し、家からサラミやチーズなどの具を持ってきて、持参のナイフでそれらを切ってその場でサンドイッチを作ってしまう光景です。あとはクスクスと香味野菜をどっさり入れた“タブレ”というサラダパスタを大きなタッパに入れてきて、紙皿に取り分けて食べているのもよく見かけました。準備を用意周到にしようとすると、外に出ることが面倒になるので、敷居を低くすることも大事だと思いました。
●その3 親も楽しむあとは親自身も楽しめる場にすることです。もしかしたらこれが習慣化のための一番の秘訣かもしれません。フランスのパパやママが公園で何をしているかと言えば、メインはおしゃべりです。もちろん子どもが小さくて親にべったりというご家庭は、一緒に砂場に入って遊んでいますが、子ども同士で遊べる年齢になったら、大人はシートを敷いておしゃべりしたり、何かを食べたり。フランスも日本同様に共働きが多いので、平日は子どもと一緒にゆっくり外で過ごすことは難しいと思いますが、その分休日に太陽の下で上手にリフレッシュしているのを感じました。外に出ることを自分が楽しいなと思えることは長続きさせるポイントだと思います。
以上、外遊びを増やすための工夫についてお伝えしてきました。内容的には小さい子のいるご家庭向けですが、体を動かすことは小学校以降もとても大事なことです。放課後は塾や習い事などで忙しかったりと、段々とインドア志向になりがちですが、1日をトータルで考えれば、目や頭ばかりを使うよりは、体全体をバランスよく動かした方が健全ですので、ぜひ幼少期に外遊びの習慣を作り、それを継続していってほしいと思います。

育児相談室「ポジカフェ」主宰&ポジ育ラボ代表
イギリス・レスター大学大学院修士号(MSc)取得。オランダ心理学会(NIP)認定心理士。ポジ育ラボでのママ向け講座、育児相談室でのカウンセリング、メディアや企業への執筆活動などを通じ、子育て心理学でママをサポート。2020年11月に、ママが自分の心のケアを学べる場「ポジ育クラブ」をスタート。著書に「子育て心理学のプロが教える輝くママの習慣」など。HP:https://megumi-sato.com/