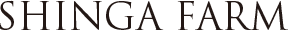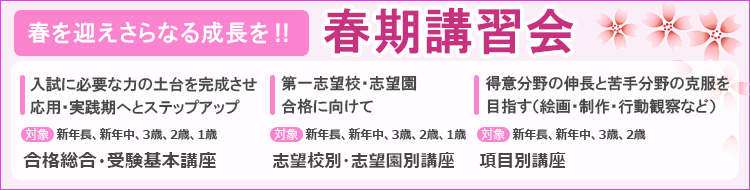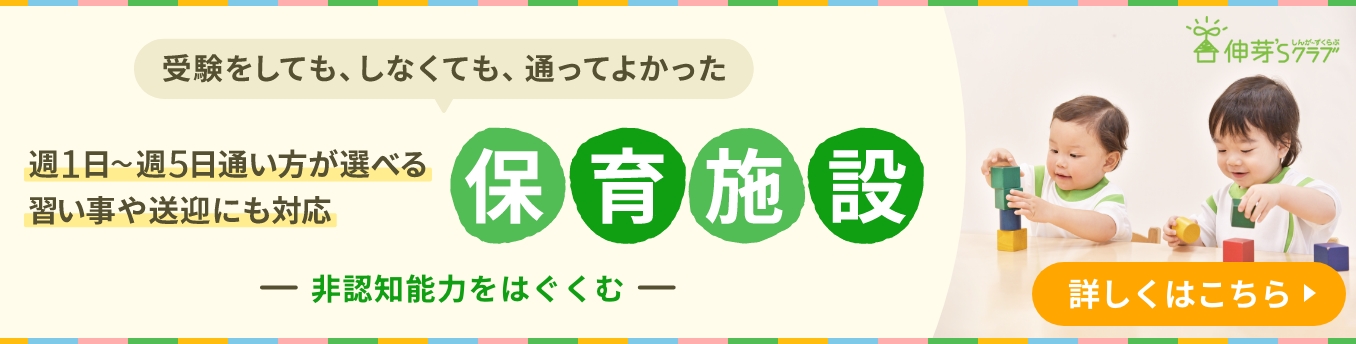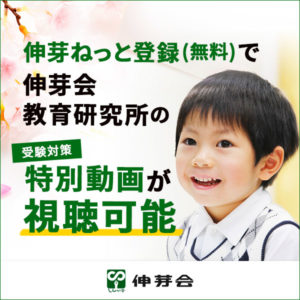学習習慣は歯磨きと同じ!? わが子を“勉強嫌い”にさせない育て方
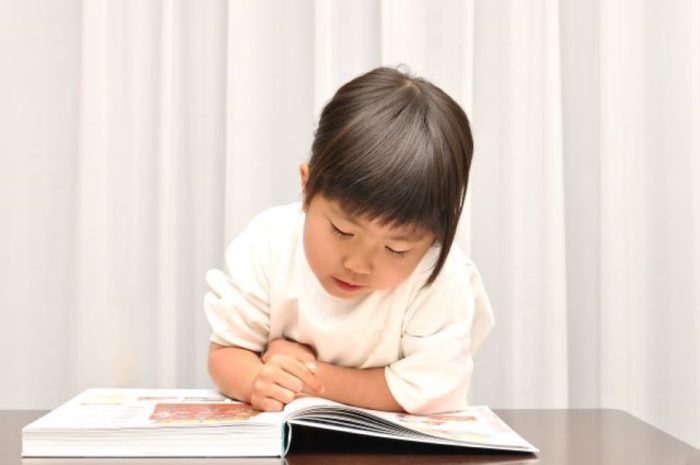
東大生たちは、ご両親から「勉強しなさい」と言われた記憶がない人が多いと言います。
そこにはどんな理由があるのでしょうか。伸芽会の牛窪先生に、「将来わが子を勉強嫌いにさせないコツ」についてお聞きしました。コツは、幼児期に自ら学ぶ習慣や楽しさをどう身につけるか。最終的には、歯磨きと同じくらい勉強をすることが当たり前になるのが理想だそうです!
目次
勉強嫌いになる子と好きになる子の違いは「親が8割」
__勉強嫌いになる子と好きになる子はどこが違うのでしょう?
某私立女子一貫校に通っていたAさんは、高校の海外ボランティア研修で法律に興味を持ち、そこから国際弁護士を目指すようになり、指定校推薦で他大学の法学部に進学しました。それまで確実に積みあげてきた学力があったからこそ、やりたいことが見つかったときに道が選べたのです。このように、一部の人をのぞけば、勉強は人生の選択肢を広げる手段でしかありません。特に幼児期にどんな環境を与えるかは親次第ですから、勉強が好きになるか嫌いになるかは、幼少期の親の影響が8割と言っても過言ではないかもしれません。
本来幼児期にプリント学習などの勉強は必要ありませんから、何かを「やらせる」のではなくて、楽しみながら一緒に考えたり褒めたりしながら、学びの土台を幼少期に作っていくことが大事なのです。
もちろん、日常生活の中で、親御さんたちが「本や新聞を読んだり、ニュースを見たり、知らないことを調べたり、夫婦で意見し合うなど、自然に学ぶ姿をお子さんに見せているか」という環境も左右します。
学習習慣は歯磨きと同じ!?
__学習習慣はどうすれば身につきますか?
2~3歳の子のかけっこをイメージしてください。何も教えなくても足が速い子もいれば遅い子もいますよね。学習も一緒です。もって生まれた能力で、教えなくもプリントを簡単に解ける子と解けない子がいます。大事なのはここからです。かけっこが遅い幼児に無理やり走らせないですよね。まずは散歩をしたり体操をしたりして体力作りをし、「早く走れるようになりたい」というモチベーションを育て、ある時期で追い越せるようになるのです。
また、学びを習慣化させるには、歯磨きとも似ています。最初から上手にできる子はそういいませんが、毎日コツコツ練習するうちに、「やるのが当たり前」になり「特別なことではない」となるのです。逆に、「うちの子は勉強ができる!」と勘違いして何もしなければ、ある程度の年齢で伸び悩むことになります。
幼児期の家庭学習で意識したい2つのこと
__幼児期の家庭学習では具体的にどんなことを意識すればいいでしょう?
幼児期はいかに「学びが楽しくなるか」が大事です。そのためには、2つのポイントがあります。
ポイント1 その場の理解より定着を重視する
幼児は大人と比べて経験値が圧倒的に少ないので、プリントの中だけでは理解できません。シーソーをやったことがなければ重さ比べは理解できないはずです。そういった実体験を大事にしながら、幼稚園や保育園、幼児教室など集団での体験によって理解を深めたり「自分もやってみたい」とモチベーションをあげ、繰り返していくうちに知識が定着していくのです。家庭学習では、理解よりも定着させることに重きをおきましょう。
ポイント2 リズムを作る(決めた時刻で始め、終わる)
幼児は眠くなったら寝る、お腹が空いたら食べるなど、本能で生きているため、体内時計がまだ備わっていません。そこを日本標準時の24時間にそろえる必要があります。
毎日決まった時間に起きて、寝る。学習も決めた時刻で始め、終わる(夕方は疲れてしまうので5分でも10分でも朝が効果的)。学ぶ際も、問題を聞き、考え、答えるというリズム作りを意識してみましょう。その際、親も終了時刻を守ることを忘れずに。「今日は調子がいいからもっとやろう!」はNGです。
「花丸で始まり花丸で終える」作戦!
__飽きたりぐずりがちな幼児との学習を、楽しく集中して行うにはどうすればいいですか?
一般的に幼児期の子どもの集中力は年長でも10分〜15分程度ですから、親がいかに子を巻き込んで褒めて、楽しく遊んでいるように感じさせるかが大事です。具体的には、得意な分野ではじめて終わる「花丸で始まり、花丸で終える」作戦です。
声かけも、「よく頑張ったね」と今できていることを褒めるようにしましょう。くれぐれも「なんでこんなのもできないの!」にならないように。1度で理解できなくても、毎日少しずつ繰り返しながら定着させていけば大丈夫です。こうした家庭学習の習慣化は、小学校以降でゼロから身につけるのは難しいので、ぜひ幼児期からコツコツとやっていきましょう。最終的に歯磨きのように、「やってないと気持ち悪い」と思うくらい、当たり前になるといいですね。
「どうして勉強しなきゃいけないの?」への答え方
__「どうして勉強しなきゃいけないの?」にはどう答えればいいでしょうか?
前述した通り、小学校低学年までのお子さんには、あれこれ説明せずに「やるのは当たり前」として親御さんも一緒にやればOKです。
ところが、いろいろなことを理解できる小学校4~5年生(個人差はあります)になるとこれが通用しなくなってきますから、どこかできちんと人生観を交えて話す時期です。将来の夢のこと、頑張りたいことなどを交えて、「これから先やりたいことを叶えるためには勉強や練習は避けては通れない」ということを話し合ってみましょう。
ただし、親自身が腑に落ちていないことは伝わりませんから、あくまで真摯に! その結果、「宇宙飛行士になりたい」「オリンピック選手になりたい」「コンクールで入賞したい」など、具体的な目的が出てきたら、「それは無理だよ」ではなくて、「そのためには、このようにやれば良いのだよ」と具体的に示し、学習意欲につなげていけばいいのです。
勉強が嫌いになるきっかけとその解消法!
__ずばり、子どもはどんなきっかけで勉強が嫌いになるのでしょう?
勉強が嫌いになるのは、できなかった問題を、「どうしてここ間違えたの!」と責められたときでしょう。あてずっぽうで当たったときもありますし、体験が少なくて理解できないときもあります。そもそも、どうして間違えたかの理由が説明できる子はもう理解できているということですよね。経験上自分が間違えた原因・理由が明確に答えられるのは小学校3、4年生だと思います。答えられないうちにどんどん親御さんが怖い顔になって、嫌な気持ちが増して、「もうやりたくない」「苦手」となるのです。
解消法は2つあります。
その1 体験を増やす
幼児の問題は体験できることが多いですから、できなかった問題の体験を増やせばきっかけがつかめるはずです。たとえば、何かを人と分ける体験が不足していると、例えば「絵の中の飴を3人で分けましょう」という問題もピンとこないでしょう。
その2 難易度を下げる
何かを学ぶ場合、大人も子どもも難しすぎても簡単すぎても成長しません。「あとちょっと頑張ればできそう」という負荷をかけることが大事なのです。ですから、どこかでできない限界がきたら、難易度を落として「できる!」という自信を再度積みあげることが必要です。私はこの「できると思える自信の積み上げ」のことを「花丸貯金」といっています。今どこにつまづきがあるかを見つけてまた戻ればいいのです。難しい問題を解かせたくなる気持ちも分かりますが、引き返す勇気はとても重要です。最後に合格を勝ち取っていくのは、基礎を徹底して積み上げ、定着させてきた子なのです。
小学校受験の合格発表の日に必ずやってほしいこと
家族で勝ち取った小学校受験の合格。もちろん大喜びして良いのです。ですが、それまでやったプリントを全部捨てて、「今日からもう何もしなくていいよ!」とテレビもゲームもし放題……。その結果、入学した時点でもう追いつけないほど、他の子と学習意欲の差が開いてしまうお子さんが、毎年多数いらっしゃるのも事実です。
ですから、私は「合格発表の日こそ、量を減らしてもいいからいつもの学習をしてください」とお伝えしています。せっかく身についた学習習慣も、6歳にして「試験がないならやらなくていい」になったら残念ですよね。逆に、この日にもいつもの学習を当たり前のように行った子は、「試験の結果に関係なくいつもやるもの」となるわけです。
SHINGA FARM(シンガファーム)編集部が執筆、株式会社 伸芽会による完全監修記事です。 SHINGA FARMを運営する伸芽会は、創立半世紀を超える幼児教育のパイオニア。詰め込みやマニュアルが通用しない幼児教育の世界で、毎年名門小学校へ多数の合格者を送り出しています。このSHINGA FARMでは育児や教育にお悩みのご家庭を応援するべく、子育てから受験まで様々なお役立ち情報を発信しています。
X(旧Twitter)、Instagram、Youtubeちゃんねる、Facebookにて最新更新情報やオリジナルの動画コンテンツを発信中!ぜひフォローください♪