
愛情の3つの柱で「わが子への愛情」のバランスをチェック!
「親の子どもへの愛情」っていったいどのようなものなのでしょうか。 子どもには、愛情を注いで育ててきたつもりだったのだけど、愛情不足や過保護を指摘されたり、集団生活に馴染めず「愛情の注ぎ方が間違っていたのでは……」と悩む...
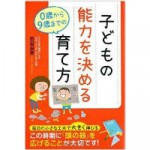
公立幼稚園、小学校での勤務、幼児教室を7地域で展開、小児病棟への慰問、子どもの声を聴く電話相談など、多方面から多くの子どもに関わる。そのような中、子育てに熱心な
故に、その愛情が焦りとなり挫折、絶望感を抱いている親子が多いことに心を痛める。
「子どもの自立」「自己肯定感」「自己制御力」を柱とし、真に子どもの能力を開花させる子育て法を広める活動を2010年から始める。
現在、息子は大学病院で医師として、娘は母子支援の職場で相談員として勤務。実生活に落とし込んだ、親の心に寄り添う記事に定評がある。「難しいことを分かり易く、ストンと腑に落ちて行動に移せること」を理念とし、現在は執筆、講演、幼児教室を中心に幅広く活動中。
資格:小学校教諭・幼稚園教諭・保育士・日本交流分析協会 子育ち支援士
著書:『子どもの能力を決める0歳から9歳までの育て方』(株)KADOKAWA

「親の子どもへの愛情」っていったいどのようなものなのでしょうか。 子どもには、愛情を注いで育ててきたつもりだったのだけど、愛情不足や過保護を指摘されたり、集団生活に馴染めず「愛情の注ぎ方が間違っていたのでは……」と悩む...

あんなに「ママ、ママ!」と後追いしていた可愛いわが子が、ある日突然「自分でする!」「あっちいって」「一人で行くからついてこないで!」と言い出す時期。そう、親離れはある日突然やってきます。 心にぽっかり穴が開いた「空の巣...
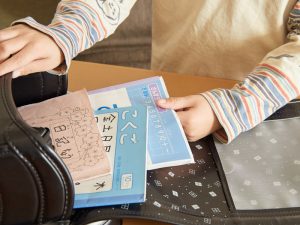
幼稚園でも小学校でも心配な忘れ物。特に小学生になると、ランドセルの他に、体操服や絵の具、習字セット、給食のエプロンなど、必要な用具や副教材も多くなります。 成績表の生活欄には「忘れ物」についての項目が設けられていること...

子どもには、2歳前後に表れる第一反抗期、いわゆるイヤイヤ期や、思春期に表れる第二反抗期があります。自我の芽生えやアイデンティティの確立で、どちらも子どもの発達段階で通る一過性のものです。 そこへ、最近は7歳児、小学校低...

最近「子育て」に関わる人は、ほとんどと言っていいほど、「自己肯定感」「自尊感情」という言葉を使われるようになってきました。そして「いっぱいほめて、子どもに自信をつけさせ、自己肯定感を高めましょう」のような言葉も、耳にする...

7月も半ばになると、目の前に迫った夏休みに、子どもはワクワクしていることと思います。普段の生活とは違う長期の休みをぜひ、有意義に過ごしたいものです。 この時期に、苦手科目の学習などの認知されるスキルを見直し高めることは...

日本の子どもは、諸外国に比べ自己肯定感が低いという調査結果が発表されています。(内閣府「子ども・若者白書」国際比較からみえてくるもの2014年)。子どもの頃、「親に認めてもらえなかった」「愛されなかった」「大切にされなか...

「非認知能力」という言葉をご存知でしょうか。最近しばしば耳にするようになってきました。将来大人になってから、社会的、経済的に成功をもたらすのは、この非認知能力が大きく影響をしていると、外国で研究が進められ、今、日本でも注...

「子どもが言うことを聞かなくて、困っている」このように感じる親御さんは、案外多いのではないでしょうか。ただ一概に「言うことを聞かない」と言っても、その状況、内容、頻度等、背景や状況が異なり、さまざまです。ですが親が「困っ...

最近「自己肯定感」という言葉をよく見聞きするようになりました。 「自己肯定感が高い子どもは、集中力がある」「意欲的である」「強い精神力を持っている」など、一度は耳にしたことがあると思います。どれも前向きな感情で、子ども...